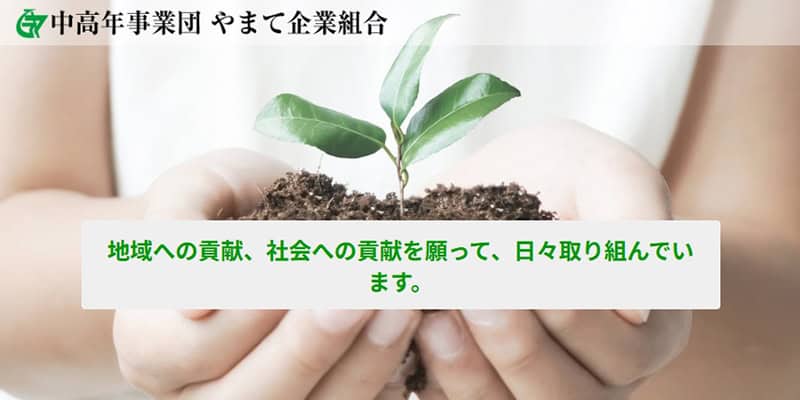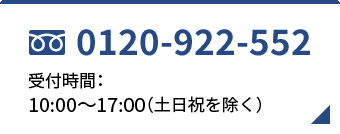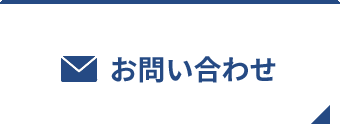福祉職だからこそ、職員のウェルビーイングを意識した職場環境づくりを。EAPサービス活用で社内のセルフケア意識の啓発・向上に取り組む

中高年事業団 やまて企業組合
人事部 部長
西原 国明 様
人事部 労務課
髙取 真珠 様
自社紙ベース・エクセル管理にかかっていた工数を削減。WEBで効率よく安全な実施が可能に。EAP活用で社内外の相談体制が整備できた
「ソシキスイッチ ストレスチェック」サービス導入の背景を教えてください
ストレスチェックが義務化された当初は、厚生労働省のキットを使って紙で実施・回収し、それをエクセルで集計をして高ストレス者を出していました。当時は紙ベースの実施とエクセルでの管理に工数がかかっていたこと、フィードバックがうまくできていなかったことに課題を感じていました。また、手作業で行うことによって見落としやヒューマンエラーが出てしまったり、所属長を経由しての配布・回収に懸念を感じて受検しない人がいたり。そうするとストレスチェックを実施する本来の意味がきちんと果たされてないのではないか、それなら完全に外部に委託して、WEBなどで効率よく、かつ、きちんとしたデータを取りながら本人にもフィードバックできる方法を取ったほうがよいのではないかと考え、当時の担当者が御社を含めて何社か候補に挙げ、色々と検討しました。
弊社ストレスチェックサービス採用の決め手は何だったのでしょうか?

決め手となったポイントの1つ目は、受検をした後に本人へのフィードバックがその場で出ること。それによりフィードバックの課題は解決します。2つ目は、WEBで実施できること。紙ベースで行うことの苦労やリスクが解消できて、安全に効果的に実施できるのではないかと考えました。
そして3つ目は、EAP社外相談窓口があること。私どもの事業の中には福祉事業部門があり、相談業務をやっていますので、やはり職員の心のケアも大切と考えています。そこで所属長や上司には相談しにくい内容も相談できる社外相談窓口を設けていますが、社内だけでなく社外にも相談できる窓口がある体制を備えたいと思っていたので、それが全て網羅されているのが御社のサービスでした。他に検討した会社も相談窓口などを用意しているところはありましたが、相談の受付や方法などに各社特徴がある中で、私たちの事業や職員の働き方を想像したときに、御社のサービスがよりなじみやすいのではないかと感じ、コストパフォーマンス面でも比較的バランスがよかったことが率直な決め手となりました。
また、御社は導入に際しての説明がかなり丁寧だったという印象もありました。例えば、EAPサービスで毎月発行される『みんなの相談室だより』など、導入後に提供されるツールの活用の仕方がイメージしやすかったことも大きかったと思います。
EAPサービスの『みんなの相談室だより』を社内に掲示。ストレスに関する知識やセルフケア情報の定期的な発信で社内の意識・啓発を強化
実際に「ソシキスイッチ ストレスチェック」サービスをご利用いただき、いかがでしたか?
私どもの団体は所属している職員の年齢が高めなので、インターネットに馴染みがあまりない方も多く、実は利用する以前からWEB受検に抵抗がある方もいるのではという懸念は多少あったのですが、社内ネットワークの整備が課題としてあったことと、ストレスチェックも紙からWEB受検に切り替えることが大前提だったので、大丈夫だと信じて導入しました。意外と簡単に回答できたという声もありましたが、導入当初は受検率があまり高くないことに悩んでいた時期もあります。業界的にも1人1台パソコンが支給されているのが当たり前ではなく、主な連絡ツールがいまだにガラケーだったりもするので、オフィス常設の共有パソコンや、個人の私用スマートフォンなどで回答してもらうことが多いです。ですが、2・3年前から社内のイントラネットを使い始めてからは、ストレスチェックの周知がスムーズになり、受検率の途中経過が今どのくらいかなどオペレーションの部分でも情報の共有がしやすくなったので、管理職にも関心を持っていただけるようになりました。おかげさまで、事業拡大で職員の人数は大幅に増えているにもかかわらず、導入当初より倍以上の方にストレスチェックを受検してもらえるようになりました。

集団分析に関しても、試行錯誤しながらではありますが、事業や仕事内容を考慮してグループ分けを変えてみたりもして、各職場の状況をできるだけ正確に把握・分析することで今後の職場改善に役立ててもらいやすいように工夫しています。衛生委員会で全体の集団分析結果を共有するだけでなく、いくつかの拠点を管理しているエリアマネージャーには各拠点のレポートを共有し、マネジメントしていく上での参考にしていただけるよう伝えています。やはり具体的な数値が見えてくることで管理職の意識づけにつながっていると感じており、ストレスチェックのデータを確認しながら振り返ることを繰り返してきた、その積み重ねが受検率の向上にも表れていると思っています。
私どもは生活困窮者支援事業を扱っているので、生活保護を受給されている方の支援業務や、生活困窮者自立支援法による住居確保給付金の手続き支援などの担当は特にコロナ禍の時期に大きな影響を受けました。接触を避ける風潮の中で対人支援ができなくなってしまったり、逆に給付金の申請・受給を希望する方からの相談対応が急増したり、業務による負担の増減でストレス状況も二極化し、ストレスチェックの結果・高ストレス者割合の変化にも直結しました。高ストレス者判定が出た方については、産業医面接の希望を聞くのと同時に、自分自身でもできるセルフケアにも目を向けてほしいなと思い資料を送っていました。その際に活用させていただいたのが、情報基盤開発さんの『みんなの相談室だより』でした。セルフケアに関する情報などが載っているお便りは、毎月各事業所で掲示しているので、職員の皆さんに見ていただけていると思います。
今後の「ソシキスイッチ ストレスチェック」サービスの活用についてお聞かせください
職員の定着、早期離職・退職につながることがないようにフォローできる環境の整備が必要だと考えているので、そのためには今後より一層、ストレスに関する知識やセルフケアなどの情報の定期的な周知をして、働きやすい職場づくりを目指すための意識啓発には力を入れていきたいと考えています。
ストレスチェックは結果も大事ですが、それよりも定期的に実施することと、その情報発信を通じて職員や管理職に意識をしてもらえるよう啓発していく意味も大きいと思っています。この1、2年は特に、職員さんの働く環境をよりよくしていくことをイメージしながら情報を発信してきました。今回ストレスチェックの数値が良好だったことや受検率が徐々に上がってきたことは、それらの取り組みが成果につながったのかなと思います。やはりストレスはどうしても発生してしまうものなので、定期的にストレスに関する情報や社内外の相談窓口を周知することが大切です。御社のコラムにも「今月は○○月間」などその時期に合わせて意識してほしいことや情報が載っているので、それを掲示することも啓発につながりますし、管理職にもきちんと話を聞いていくこと必要だと伝わると思っていますので、今後も引き続き活用させていただきます。また、職員のウェルビーイングを高めるためには仕事に対するモチベーションも大事なので、所属長面談にモチベーション管理の視点を取り入れたり、年二回の決められた面談以外にも必要に応じて声かけをしたり、他にも自分の性格をきちんと理解した上でどういったことがストレスになるのかを理解できるようなツールを導入したりなど、チームビルディングを行っていくための仕組みの「見える化」を進めています。
チームで自立支援を進め「社会資源にきちんとつなげていく」仕事。だからこそ大切なのは職員が相談しやすい環境づくりとスムーズな情報共有・周知
貴社の職場環境改善に向けた取り組みについて教えてください
グループが事業を拡大していく中で、以前は小さな規模で行っていた本社機能を部門化して、数年前に人事部が新しくできました。この人事部ができてから、「コミュニケーションの強化」と「社内ネットワークの整備」を進めてきました。

そもそも相談業務に対応する職員は「チームで仕事をする」という意識が高いと思っています。また働く職員の年齢層が高めの組合でもあります。平均年齢は48~49歳くらいで、60歳以上の方が三分の一はいるような組合です。それもあってか、いわゆる飲み二ケーションのような勤務を離れた後の交流も比較的よく行われており、福利厚生の一環として費用を出して組合が推奨しながら交流の場を設けていることが前提としてあります。交流が活発なこともあり、各職場の上司や一緒に働く同僚に相談でき、ちょっとした愚痴をこぼしやすい環境はあると思います。業務を行う中では理不尽なことや壁にぶち当たることも多いのですが、事業所に戻ってくると話を聞いてくれる人がいる、そういうストレスを抱えても打ち明けられる人がいる職場ではあると思いますね。それでも高ストレス者の判定が出ることはありますが、そういった場合には、個別に管理職が面談、もしくはミーティングの場で改善をするためには何が必要かのヒアリングをきちんと行っています。規模の大きい事業所の場合は、一部で昨年ごろから、3か月に1度の精神科医によるスーパービジョンを取り入れ、相談員の話を聞いてもらう場を設けました。
年末には組合全体の納会を開催しており、昨年は参加職員へ組合についての社内研修を実施しました。人数もだいぶ増えてきたので、改めてグループ全体の歴史や福祉事業部門ができた経緯を代表者から伝え、組合全体の動きや新しい取り組みを含めて、我々の目指すところやチームで関わる共通の視点を職員に周知しました。同じ法人の中でも自分が関わっていない事業は実はたくさんあると思うので、例えば、お金に関する支援をしている事業もあったり、就労に関する支援している事業もあったりとさまざまなのですが、いくつかをピックアップして、実際に従事している人から現場の話を聞くことを通して理解・啓発にもつながったのではないかと思っています。研修の後は忘年会という形で大多数の職員が参加して交流を深めることも大切にし、研修要素を強化しながらもコミュニケーションの場として実施しています。
長年の課題だった社内のネットワークの整備は、今もまだ引き続き課題は残っていますが、2、3年前から社内のイントラネットを使い始めたことで色々なことが周知・共有しやすくなりました。ICT部門ができたことでインフラの整備がだいぶ進み、適切な情報周知に必要な体制の面でも、例えば人事部でも労務と人材開発を部署として分けて業務ができるようになり、整いつつあります。ただ、ストレスチェックのところでもお話ししましたが、業務中の連絡手段として主に使用しているのがガラケーだったり、社内ネットワークが使えない事業所がまだ一部にはあったりするので、社内の情報をきちんと現場の職員全員と簡単に共有できる仕組みをきちんと構築していくことが、我々の事務局全体の急務の課題だと思っております。
こういったことをお話ししながら振り返り、次の課題に取り組めるのも、社内のネットワークがちゃんとできてきたからかなというのがあります。外部のシステムを導入したことで、メンタルヘルスケアに関する情報の回覧・周知、社内メールや経費精算もできるようになり、スケジュール管理に関しても、例えば他部署の人の予定が以前はわからず確認に時間を要していたのが、今では「見える化」されました。その重要性をすごく理解をしていますので、今後も引き続ききちんとやっていくことが大切だと考えています。
対人業務の中でも特に、福祉事業部が対応している業務はなかなかオンライン化が難しいものです。カウンセリングだけであればオンラインでもできるかもしれないですが、我々は「社会資源にきちんとつなげていくこと」が一つの大事な目的にありますので、場合によっては同行支援も必要になってきますし、何度もお会いする、もしくは、訪問することもあります。コロナ禍で一部強引に進めたオンライン化も、対人業務は元に戻っています。引き続き対面での支援が必要な事業と、給付金等で相談が増加した事業・行政からの受託事業などいずれにしても社会のニーズが増え、事業規模も大きく拡大しています。さまざまな難しさを抱えることも多いですが、働きやすい環境を整備することによって受けるストレスをなるべく軽減し、高ストレスが原因で早期離職・退職につながることがないような職場づくりを目指していきたいと思います。
ストレスチェック大賞 2024:業界・部門別優秀賞受賞
ソシキスイッチ ストレスチェック
(旧称AltPaperストレスチェック)お申し込み・ご相談 お気軽にご相談ください
- キットのみも
ご購入いただけます - キットを購入する